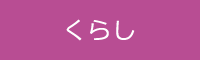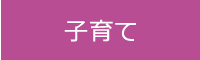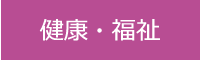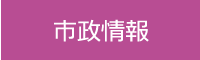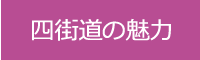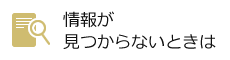四街道市自然環境保全地区
更新:2025年7月7日
四街道市自然環境保全地区とは
このまちの豊かな自然を「みんなで未来に引き継ぐ」ための場所
四街道の自然の大部分は、谷津田と一体となった樹林や水路等からなる「里山」で占められており、この「里山」こそが、四街道の生きものが暮らすための基盤にほかなりません。
市内では実際に、ヘイケボタルやオオタカ、クマガイソウ等の、里山に適応した希少な動植物の生息・生育が確認されています。
また、「里山」を主として構成される豊かな自然環境は、私たちの暮らしの潤いとなるだけでなく、生物多様性の源となり、気候変動の影響を緩和する等の多様な機能を有しているため、四街道の魅力の1つとして、「みんなの手で未来に引き継いでいく」ことが大切です。
しかし近年では、農業従事者の高齢化に伴う農地面積の減少等が原因で、耕作放棄地や手入れが行き届かない樹林が増える等、「里山」の質の低下がみられます。
このような背景を踏まえ、第3次四街道環境基本計画に基づく「重点取組」として、特に自然環境を保全する必要があると認められる場所を「四街道市自然環境保全地区」として選定し、魅力ある豊かな自然を将来にわたって保全するよう、様々なことに取り組んでいきます。
自然環境を保全するための「5つの柱」
自然環境保全地区では、保全のための5つの基本方針のもと、環境保全活動に取り組みます。
里山景観の保全
豊かな里山景観を維持・再生するため、谷津田や湧水、斜面林等の多様な要素を一体として保全します。
生物多様性の保全・回復
里山に生息・生育している多様な生きものと、その生態系を保全・回復するよう取り組みます。
水源の保全
台地の地下水涵養機能を保全しながら、ごみの不法投棄を里山の活用によって防止し、水源地としての機能を保ちます。
(注釈)「地下水涵養」とは、雨や河川等の水が地下に浸透し、地下水として供給されることをいいます。
環境学習の場としての活用
自然や環境保全活動への興味・関心を高められるような場所として活用し、正しい理解を促進します。
協働による取組の推進
土地の所有者、環境保全活動団体、市役所など、みんなで協力して、環境保全活動等の様々なことに取り組みます。
自然環境保全地区として選定した場所
山梨地先(山梨ほたるの里)
山梨地先(山梨ほたるの里)

市職員も整備活動に参加しています
- 所在地
- 四街道市山梨1940付近
- 面積
- 約2,050平方メートル
- 概要
- ホタルの自然観察地として市が長年借り上げ、市民団体の方とともに整備してきた「山梨ほたるの里」ですが、近年ではホタルの観測数が減少傾向にあるほか、アカガエル等の生きものがほとんど確認されなくなる等、自然環境に変化が見られていました。
- こうした状況を受け、令和7年6月24日に、この場所を初めての自然環境保全地区として選定しました。
「みんなで」自然環境を守るための我が国の取組
四街道市では、「自然環境保全地区」の選定を通じて、土地所有者や環境保全活動団体の皆様と一緒に、このまちの自然環境の保全に取り組みますが、国(環境省)では、「30by30」の達成に向けた「自然共生サイト」の認定を通じて、事業者や民間団体等のあらゆる主体により自然環境が保全されるよう取組を進めています。
30by30とは
「30by30」とは、2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的な目標のことです。
この目標は、2022年12月に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で大きな目標の1つとして掲げられ、これを受け国(環境省)においても、2030年までに生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること(ネイチャーポジティブ)を実現するための目標の1つとして位置付けています。
国は、国立公園や自然公園等の「保護地域」と、保護地域ではないものの生物多様性保全に貢献している区域である「OECM(Other Effective area-based Conversation Measures)」の確保による「30by30」の目標達成を目指しています。
自然共生サイト
国は、令和5年度から、30by30の達成のため、保護地域内外を問わず、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を、「自然共生サイト」に認定しています。具体的な例としては、企業の水源の森、ビオトープ、里地里山、森林施業地、企業敷地等における緑地、研究や環境教育の森林等のうち、生物多様性の保全が図られている場所が対象となります。
「自然共生サイト」に認定された区域は、30by30の達成度評価のために運用されているOECM国際データベースに登録されます。