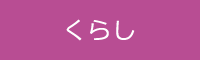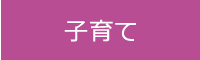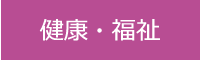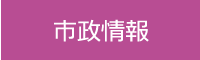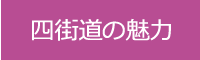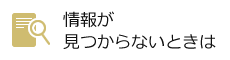定額減税補足給付金(不足額給付金)について
更新:2025年7月10日
制度の概要
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
不足額給付の対象者
四街道市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で四街道市に住民登録のある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方。
支給対象となりうる方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、扶養親族に該当しない方(例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(3万円給付を除く)
上記ほか、
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」
(注1)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注1)1・2・3のいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当し
ていない者を指します。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付額
不足額給付1
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)
支給・申請方法等
支給・申請方法については以下のページをご覧ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、コールセンターへお願いします。
(課税課ではお答えしておりません)
電話:043-421-6165(受付時間 9時から17時 月曜から金曜日:祝日を除く)